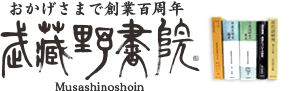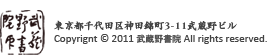ホーム > 書籍案内 > 研究書(語学系) > 日本語学シリーズ③「現代語」学
研究書(語学系) 詳細
日本語学シリーズ ③「現代語」学
| 書名かな | にほんごがくしりーず さんげんだいごがく |
|---|---|
| 著者(編者)名 | 藤原与一 著 |
| 著者(編者)名かな | ふじわらよいち |
| ISBNコード | 978-4-8386-0174-5 |
| 本体価格 | 7,000円 |
| 税込価格 | 7,700円 |
| 判型 | A5判上製カバー装 |
| 頁数 | 302頁 |
| 刊行日 | 1997年11月3日 |
| 在庫 | 残部僅少 |
緒言
前編 国語研究の理念と方法
〇 はじめに(学問一般についての基礎的弁別)
Ⅰ 国語研究は何を目的としたらよいか
一 目的は自己にかかわるもの
二 国語研究の必要
三 そのものを知る
四 科学的究明
五 人間生活・社会生活との関連においての,
言いかえれば,生活現実との関連においての科学的究明
言いかえれば,生活現実との関連においての科学的究明
六 現代人の国語生活の発展への寄与
七 国語観
八 国語研究目的のもとでの個人の態度
Ⅱ 国語観
一 言語とは何か
二 母語
三 母語認識
四 自己にとっての国語実態
五 生活語観
六 言語表現観
七 観の生成
Ⅲ 国語研究に関する諸問題
一 対象上にどのような問題があるか
1 言語と非言語
2 自然言語と機械言語
3 外的言語と内的言語
二 方法上の諸問題
1 客観的方法と主観的方法
2 割りきること
3 特殊的方法と普遍的方法
4 演繹的方法と帰納的方法
Ⅳ 「国語学」の概念
一 国語学は人文学と自然学との基礎学である。
二 国語学は実証の学である
三 国語学は,一面,資料学(事実学)
として規定されるものである
として規定されるものである
1 資料学―→ものの学問
2 ものの学問とかたちの学問
3 調査
4 資料と説明
5 事実の学問(事実学)
6 資料の世界
7 資料処理の厳密
四 国語学は,「二」ゆえに,一面,
記述学として規定されるものである
記述学として規定されるものである
1 実証の学ゆえに記述額になる。
2 最初の記述
3 記述と思考
4 書いてながめる
5 「記述」の例説
6 記述推進の実際
7 記述の仕方としてのノート法・カード法
8 記述の精神
9 純粋記述
10 記述即説明
11 記述体系
12 記述からの独創
五 国語学は人間の学である
1 人間文化の学としての国語学
2 人間精神の学としての国語学
3 人間社会の学としての国語学
4 人間の学としての国語学
Ⅴ 国語研究者
一 人間言語の学と国語研究社
二 愛情
三 個性の自覚
1 知的と情的
2 客観的態度と主観的態度
3 分析的な見かたをするタイプと
包括的な見かたをするタイプ
包括的な見かたをするタイプ
4 回顧的と展望的
5 つめたい人間とあたたかい人間
四 調和的人格
五 研究の個性化
六 生活者 国語研究社
Ⅵ 生活即学問
一 言葉の学問
二 研究の生活化
三 私のばあい
四 国語学の性格
Ⅶ 国語研究の世界とその諸領域
Ⅷ 研究参考書
一 総説書
二 部門別参考書
三 傍系参考書
四 第一級の参考書を
五 自己の生活の中に諸種の参考書がある
六 書かれたものと話されたもの
七 雑誌論文について
八 辞書・事典の類について
九 参考書(→参考文献)の利用法について
―参考書の読みかた―
―参考書の読みかた―
Ⅸ 研究対象の把握
一 研究対象
二 「把握」の意味
三 把握の進展
四 研究主題の確立へ
五 方法と対象との相関
六 対象世界――国語というもの――
Ⅹ 研究方法
一 方法の基礎
1 身辺照顧(環境整理)
1’ つまらぬこと
2 態度
3 言語感覚の錬磨
4 問題感覚の振起
二 方法の合理化
三 方法―→分析
四 方法―→比較
五 方法―→体系化
六 方法―→対象に即して実証的に高められるもの
七 手段―→方法のための手だて
Ⅺ 研究の独創
〇 結語
本編「現代語」学
第一章 総説
一 学問
二 国語学の目的
1 国語とは何か
2 国語研究の学問
3 国語学の目的
4 現代語へ
5 私の目的意識
6 方言学 国語学
三 対象と方法
1 研究の対象
2 研究の方法
3 国語研究の方法 甲
4 国語研究の方法 乙
5 「方法論→方法」の明確
四 「現代語」学の体系
1 研究の体系
2 これまでに見られた国語学関係の研究体系
2’ 研究体系一般についての私の努力目標
3 私の国語学体系
4 「現代語」学の研究体系
五 周辺(関連)諸学
1 第一周辺学として,
いわゆる国文学を指摘することができる。
いわゆる国文学を指摘することができる。
2 第二周辺学として,
精神科学系の諸学を指摘することができる。
精神科学系の諸学を指摘することができる。
3 第三周辺学として,
社会科学系の諸学を指摘することができる。
社会科学系の諸学を指摘することができる。
4 第四周辺学として,
自然科学系の諸学を指摘することができる。
自然科学系の諸学を指摘することができる。
第二章 現代語の共時論的構造
第一節 序
第二節 内的構造(論その一)――〈方言の見地から〉――
一 第一次分析
1 社会意志
2 無自覚浮動の心的状態
二 第二次分析
1 表現に関する「ていねい」の好み
2 「婉曲」の好み
3 「断定保留」の好み
4 「寡言尊重」の好み
5 「うわさ」の好み
6 「あそび」の好み
7 「滑稽」の好み
8 「比喩」の好み
9 「標準」の好み
10「言語道断」の好み
11「古雅」の好み
12「美化」の好み
13「制肘」の好み
第二’節 内的行動(論その二)
――〈日本語一般の見地から〉――
――〈日本語一般の見地から〉――
一 言語――人間存在〈人間〉との共存
二 創作欲
三 模倣
四 熱狂と冷静
五 言語不信の意識
六 言語の生産性――文化性・思想性――への無知識
七 内的構造に対する要請の意識
――「論理的表現を」との要請――
――「論理的表現を」との要請――
1 「数」の問題
2 人称代名詞の整理
3 短文化
4 修飾法の整理
5 主・述の対応を旨とする
八 むすび
第三節 外的構造
一 国語現実の諸相
1 国土と国語
a 辺境性
b 日本孤
2 方言相
a 東北と南西との対応
b 中国地方の北がわと南がわ(山陰と山陽)
b’四国の北と南
c 関東地方
d 中部地方
e 近畿地方
3 共通語
4 標準語
5 階級語
二 外的構造の分析
◎ 構造論の対象
その一 音韻構造
1 音声現象と音韻構造
2 構造の分析単位
3 開音節
4 複子音・二重母音
5 等時音節
6 語の音節数
7 語アクセントの型
8 動と不動
その二 文法構造
1 文法構造の所在
2 文の文法構造
〇 二つの見かた
a 他へのはたらきかけのつよいもの
(1)願望・依頼の表現法
(2)命令の表現法
(3)勧奨の表現法
(4)禁止・制止の表現法
(5)緩急の表現法
(6)問尋の表現法
(7)よびかけの表現法
(8)応答の表現法
(9)意向の表現法
(10)反撥・抗弁の表現法
(11)推量の表現法
(12)伝達の表現法
(13)想像の表現法
(14)あいさつの表現法
b 相手を特定的には求めないもの
(15)説明の表現法
c まったく自己本位のもの
(16)感嘆の表現法
(17)唱えの表現法
3 表現形式にしたがっての下位区分
(1)命令表現法について
(2)禁止命令の表現法について
(3)勧誘の表現法について
(4)問尋の表現法について
4 文章の文法構造
(1)文連接の態
(2)段落
(3)文章と文
(4)日本語の文構造の特性に根ざした非論理文
(5)話しことばの文章と書きことばの文章
5 文法構造の不動と動
6 表現法と表現
その三 語彙構造
1 語彙・語詞の面
2 語彙の世界
3 生活語彙分類体系 試案
a 自然語彙
b 人間語彙
c 社会生活語彙
d 生業語彙
e 生活一般語彙
4 方言語彙構造
5 共通語の世界
6 語彙の流動
7 語彙中の語詞
8 まとめ
その四 表記構造
1 書きことばの問題
2 日本語の表現法と日本語の表記方法
3 たて書き・よこ書き
4 文章にあっての段落の対応
5 文章にあっての漢字と
かな(ひらがな・カタカナ)との対応
かな(ひらがな・カタカナ)との対応
6 表記面の芸術性
7 表記上の句読点
8 文章表記上の諸符号
9 抑揚面
10表記の内面
第四節 跋
第三章 現代語の通時論的構造
第一節 国土上の日本語現実
一 通時態
二 歴史的現実
第二節 言語地理学的構造
一 方言分派関係
二 分派関係の把握
第三節 歴史的法則
一 分派関係をなす歴史的現実に認められる歴史的法則
二 転化の法則
三 省略の法則
四 複合の法則
五 飛躍
第四節 発展的動向
一 「言語わく」の拡大
二 言語の創作活動の多様化
三 人工世界御の発達
第四章 現代語生活――現実と理想――
第一節 序説 ~現代語生活論の地位~
一 高次共時論のたちば
二 教育論の必至
第二節 言語生活としての方言生活·共通語生活·標準語生活
一 現代語生活
二 現代語生活の性格。
三 言語生活としての方言生活・共通語生活・標準語生活
四 方言生活
五 共通語生活
1 心の共通語を
2 方言生活卑下感の除去
3 能動の共通語生活
4 表現はすべて個別的
5 東京語批判・大阪語批判
6 むすび
六 標準語生活
1 共通語と標準語
2 共通語生活から標準語生活へ
3 現代共通語生活の様態
4 標準語体系
5 標準語生活
第三節 言語生活の自覚と 言語生活の発展
第四節 標準語体系の中の表記法
一 言語構造分子としての文字付符号
二 表記にかな・漢字を利用活用することについての小案
「正書法のしおり」
三 漢字の教養
四 表記の抑揚
第五節 表現法中心~標準語体系~
一 中核となるもの
二 表現法自覚の根本
第六説 根本日本語と精神生活
一 根本日本語
二 精神生活の発達
三 表現の法
結語
あとがき