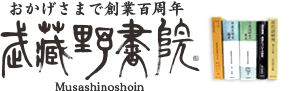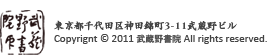ホーム > 書籍案内 > 注釈書・単行本など > 俳文紀行 おくのほそ道論釈
注釈書・単行本など 詳細
俳文紀行 おくのほそ道論釈
| 書名かな | はいぶんきこう おくのほそみちろんしゃく |
|---|---|
| 著者(編者)名 | 志田延義 著 |
| 著者(編者)名かな | しだのぶよし |
| ISBNコード | 978-4-8386-0384-8 |
| 本体価格 | 2,913円 |
| 税込価格 | 3,204円 |
| 判型 | A5判上製カバー装 |
| 頁数 | 214頁 |
| 刊行日 | 1996年8月20日 |
| 在庫 | 在庫あり ※10冊以上購入ご希望の場合には別途ご連絡下さい。 |
本書は、曽良の『奥の細道随行日記』の出現以来
「おくの細道」と「日記」との対決を進めてきた著者が、
このたびの『芭蕉自筆本』の出現校刊に先立って、「おくのほそ道」が俳文たることを改めて論釈したもの。
「岩沼に宿る」の条の戯言俳諧が貼紙下の狂歌の戯れの転化発展だったことを予見しているなど見事である。
「おくの細道」と「日記」との対決を進めてきた著者が、
このたびの『芭蕉自筆本』の出現校刊に先立って、「おくのほそ道」が俳文たることを改めて論釈したもの。
「岩沼に宿る」の条の戯言俳諧が貼紙下の狂歌の戯れの転化発展だったことを予見しているなど見事である。
目 次
はしがき
凡例
解説
一 芭蕉の俳諧の発足
二 芭蕉の文章としての紀行へ
三 芭蕉俳文の到達点『おくのほそ道』の構成・表現
四 『おくのほそ道』俳文の軽み
五 『おくのほそ道』の原本
おくのほそ道
一 武蔵の部
1 深川――芭蕉案から採茶庵へ(月日は百台の過客にして)
2 千住(弥生も末の七日)
3 草加(今年元禄二とせにや)
二 下野の部
1 室の八島(室の八島に詣す)
2 日光山の麓―佛五左衛門(此の日、日光山の麓に泊まる)
3 日光山(卯月朔日、御山に詣拝す)
(二十余町山を登って滝有り)
4 那須の黒羽へ(那須の黒羽という所に知る人あれば)
5 黒羽・那須八幡宮(黒羽の館代)
6 光明寺(修験光明寺と云ふ有り)
7 雲巌寺(東国雲巌寺のおくに)
8 殺生石(是より殺生石に行く)
9 蘆野(又清水ながるゝの柳は)
三 陸奥(磐城・岩代)の部
1 白河の関(心許なき日数重なるまゝに)
2 須賀川(とかくして越え行くまゝに)
(此の宿の傍に)
3 浅香・忍の里(等窮が宅を出でて五里斗り)
(あくれば)
4 丸山(月の輪のわたしを越えて)
5 飯坂温泉・伊達の大木戸(其の夜飯塚にとまる)
四 陸奥(陸前)の部(1)
1 笠島(鐙摺・白石の城を過ぎ)
2 武隈の松(武隈の松にこそ目覚むる心地はすれ)
3 仙台・宮城野(名取川を渡って仙台に入る)
4 奥の細道(かの画図にまかせてたどり行けば)
5 多賀城址(壺の碑)
6 末の松山・塩竃の浦(それより野田の玉川・沖の石を尋ぬ)
7 塩竃の明神(早朝塩竃の明神に詣づ)
8 雄島・松島(抑も事古りたれど)
9 瑞巌寺(十一日瑞巌寺に詣づ)
10 石の巻(十二日)
五 陸奥(陸中)の部
1 平泉―高館(三代の栄耀一睡の中にして)
2 光堂(豫て耳驚かしたる二堂開帳す)
六 陸奥(陸前)の部(2)
11 尿前の関(南部動遥かにみやりて)
七 出羽の部
1 最上の庄へ(あるじの云ふ)
2 尾花沢(尾花沢にて清風と云ふ者を尋ぬ)
3 立石寺(山形領に立石寺と云ふ山寺あり)
4 大石田(最上川乗らんと)
5 最上川(最上川はみちのくより出でて)
6 羽黒山(六月三日羽黒山に登る)
7 月山・湯殿山(八日月山にのぼる)
(谷の傍に鍛冶小屋と云ふ有り)
8 鶴が丘・酒田(羽黒を立ちて)
9 象潟(江山水陸の風光数を尽くして)
八 出羽・越後の部
1 鼠ケ関・佐渡(酒田の余波日を重ねて)
2 親知らず・市振の関
(今日は親知らず子しらず・犬もどり・
駒返しなどいふ北国一の難所を越えて疲れ侍れば)
(今日は親知らず子しらず・犬もどり・
駒返しなどいふ北国一の難所を越えて疲れ侍れば)
九 越中・加賀の部
1 黒部四十八ヶ瀬・那古の浦(黒部四十八か瀬とかや)
2 倶利伽羅が谷・金沢・小松(卯の花山・くりからが谷をこえて)
3 太田神社(此の所太田の神社に詣づ)
4 那谷(山中の温泉に行くほど)
5 山中温泉(温泉に浴す)
(曽良は腹を病みて)
6 全昌寺(大聖寺の城外)
十 越前の部
1 吉崎の入り江(越前の境)
2 天龍寺(丸岡天竜寺の長老)
3 永平寺(五十町山に入りて永平寺を礼す)
4 福井(福井は三里斗りなれば)
5 敦賀(漸く白根が嶽かくれて)
6 気比明神(その夜月殊に晴れたり)
7 種の浜(十六日空霽れたれば)
十一 美濃の部
1 大垣(露通も此のみなとまで出でむかひて)
跋
去来書写本奥書
附録 芭蕉略年譜
歌仙「馬かりて」の巻
図版