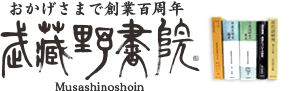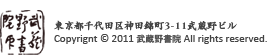ホーム > 書籍案内 > 研究書(語学系) > 断定表現の通時的研究
研究書(語学系) 詳細
断定表現の通時的研究
―江戸語から東京語へ―
| 書名かな | だんていひょうげんのつうじてきけんきゅう ―えどごからとうきょうごへ― |
|---|---|
| 著者(編者)名 | 長崎靖子 著 |
| 著者(編者)名かな | ながさきやすこ |
| ISBNコード | 978-4-8386-0263-6 |
| 本体価格 | 12,000円 |
| 税込価格 | 13,200円 |
| 判型 | A5判上製函入 |
| 頁数 | 446頁 |
| 刊行日 | 2012年9月14日 |
| 在庫 | 品切れ中 |
目次の詳細は「立ち読みする」を参照ください。
まえがき
凡例
第一部 断定表現研究序説
第一章 江戸語・東京語
第二章 断定表現の通時的研究の意味
第二部 終助詞「さ」の通時的研究
第一章 江戸語の終助詞「さ」の機能に関する一考察
まえがき
凡例
第一部 断定表現研究序説
第一章 江戸語・東京語
第二章 断定表現の通時的研究の意味
第二部 終助詞「さ」の通時的研究
第一章 江戸語の終助詞「さ」の機能に関する一考察
第二章 江戸語の「動詞連用形+て+さ」表現形式に関する一試論
―西部待遇表現「動詞連用形+て+指定辞」との関係から─
第三章 終助詞「さ」による反語表現に関して
第四章 「ツサ」の意味分析に基づく江戸語の文末表現の特徴
第五章 「のさ」の一形式「んさ」に関する考察
第六章 『浮世風呂』『浮世床』に見る断定辞としての終助詞「よ」の位相
─断定辞としての終助詞「さ」との比較から─
第七章 江戸語から東京語に至る断定辞としての終助詞「よ」の変遷
─断定辞としての終助詞「さ」との比較から─
第八章 現代語の終助詞「さ」の機能に関する考察
第三部 助動詞「です」の通時的研究
第一章 江戸後期口語資料に見る助動詞「です」の意味
─その使い手と語感を通して─
第二章 歌舞伎台帳に見る助動詞「です」の様相
─その意味と使用意図に関して─
第三章 明治初期の小新聞に見る助動詞「です」の様相
第四章 明治初期の大新聞に見る助動詞「です」の様相
─明治初期の小新聞との比較から─
第五章 洋学会話書に見る助動詞「です」の様相
第六章 明治期における助動詞「です」の普及
─演説速記資料を中心に─
第四部 その他の断定表現
第一章 江戸語における「でございます」
第二章 遊里における「であります」の使用意図
─江戸後期の洒落本、人情本の調査から─
―西部待遇表現「動詞連用形+て+指定辞」との関係から─
第三章 終助詞「さ」による反語表現に関して
第四章 「ツサ」の意味分析に基づく江戸語の文末表現の特徴
第五章 「のさ」の一形式「んさ」に関する考察
第六章 『浮世風呂』『浮世床』に見る断定辞としての終助詞「よ」の位相
─断定辞としての終助詞「さ」との比較から─
第七章 江戸語から東京語に至る断定辞としての終助詞「よ」の変遷
─断定辞としての終助詞「さ」との比較から─
第八章 現代語の終助詞「さ」の機能に関する考察
第三部 助動詞「です」の通時的研究
第一章 江戸後期口語資料に見る助動詞「です」の意味
─その使い手と語感を通して─
第二章 歌舞伎台帳に見る助動詞「です」の様相
─その意味と使用意図に関して─
第三章 明治初期の小新聞に見る助動詞「です」の様相
第四章 明治初期の大新聞に見る助動詞「です」の様相
─明治初期の小新聞との比較から─
第五章 洋学会話書に見る助動詞「です」の様相
第六章 明治期における助動詞「です」の普及
─演説速記資料を中心に─
第四部 その他の断定表現
第一章 江戸語における「でございます」
第二章 遊里における「であります」の使用意図
─江戸後期の洒落本、人情本の調査から─
第三章 文末表現「げす」の評価に関して
結び 断定表現体系の変遷─江戸語から東京語へ─
あとがき
論文初出一覧
索引
結び 断定表現体系の変遷─江戸語から東京語へ─
あとがき
論文初出一覧
索引